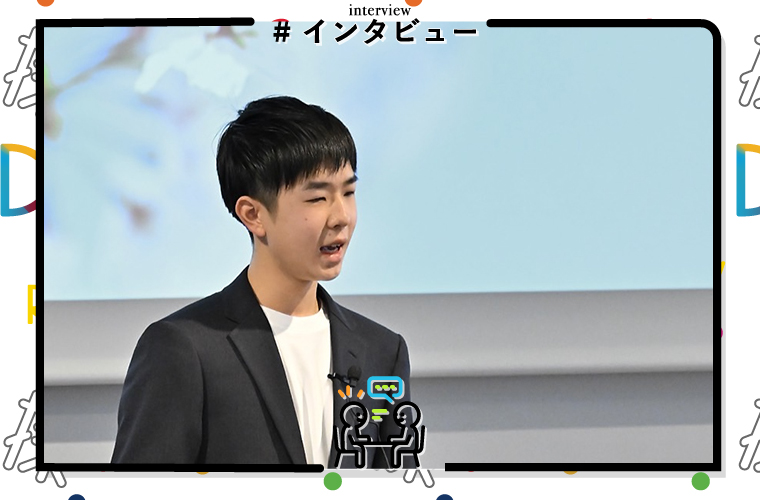
郡山女子大学附属高等学校
防災ガールズ
若い世代が防災について楽しく学べる
『郡山防災マップ』に挑戦
郡山女子大学附属高等学校の「防災ガールズ」の皆さんは、防災を自分ゴトとして捉え、若い世代に楽しく防災について学んで欲しいとの想いで、メタバースやVRを用いた「郡山防災マップ」を提案。SDGs探究AWARDS2024(以下、アワード) 清泉女子大学 協賛団体賞「地球市民学部賞」を受賞されました。東日本大震災を幼稚園の時に経験した皆さんが成長し、防災に対する社会の意識を変えるためアクションを起こしたこと。そして、メタバースやVRという技術を使い、イベントで実際に子供達に使ってもらうなど試行錯誤しながら前に進む姿勢が評価されました。今回は、3年生の市川 莉彩さん、眞弓 桃香さん。2年生の高橋 杏奈さん、土屋 ふうかさん、富塚 希和さん、1年生の佐藤 美羽さん、佐藤 俐宥さん、鈴木 綾音さん、前田 真咲さん。そして指導にあたられた水澤先生に「郡山防災マップ」を作ろうと考えた経緯や、今後の構想などについてお話をお伺いすることができました。

防災を自分ゴトとして捉えて欲しい。
チームで挑んだメタバースで作る郡山防災マップ
―作品の内容について教えてください
市川さん「私達が作成している郡山防災マップは、郡山駅周辺をイメージしたメタバースの世界(ワールド)を、危険な場所を避けながら進むという≪防災を学ぶためのゲーム≫です。多くの人に防災を楽しく、そして分かりやすく学んでもらうため、体験者にはVRゴーグルを装着してもらい、仮想空間の中を実際に歩くことで、よりリアルで臨場感のある体験ができるようにしています。」
―なぜ、防災をテーマに選んだのでしょうか
市川さん「防災の重要さを分かっていても、防災対策をしていないという人がたくさんいることを知ったことがきっかけです。そういった人達に楽しんで防災について学んで欲しいなと思い防災をテーマに選びました。」
眞弓さん「私自身、東日本大震災が起きた時はまだ3歳だったため、当時のことをよく知らなかったり、あまり覚えていなかったりします。だからこそ、3.11で起こったことを風化させてはいけないと強く思っています。
3.11を知らない世代には、あのとき何が起こり、その後もどのような影響が続いたのかをしっかり伝えていく必要があると感じています。でも、テレビやネットで見るだけでは、どこか遠い場所の出来事のように感じてしまう人も多いと思います。だから私はこの郡山防災マップを通じて、『災害はいつでも、誰の身の回りでも起こることなんだ』ということを実感してもらい、自分の命を守るための“備え”の大切さを知ってもらいたいと思うようになりました。」
―去年の秋からスタートされた郡山防災マップの活動ですが、現在の状況を伺ってもよろしいでしょうか
眞弓さん「現在、私達はこの防災マップをさらに分かりやすく、楽しく学べるものにするための改良を進めています。ワールドは郡山駅をイメージして作っていますが、訪れた人にもっとリアルに感じてもらえるよう、看板やお店のイラストなどを工夫して、より伝わりやすい表現を取り入れていく予定です。
また、この取り組みは、まだあまり皆さんに知られていないため、小学校高学年から中学生をメインターゲットに、もっと興味を持ってもらえるようなアイデアを考えています。たとえば、スタートからゴールまでの間に、防災グッズが入った『防災バッグ』を拾いながら進むというようなゲーム要素を加えることで、楽しみながら自然と防災を学べる仕組みにしたいと考えています。」
―より楽しみながら学ぶことのできる防災マップに進化を続けるんですね。
チームでは、この春から郡山防災マップの活動に新しく加わった1年生もいますが、どのような役割分担をして活動を行っているのでしょうか
眞弓さん「1年生から3年生まで、まずは皆でアイデアを出し合いながらプロジェクトを進めています。その後、役割を分担していき、プログラミングを担当する人、さらに詳しいアイデアを考える人、イラストを描く人などに分かれて活動します。それぞれが自分の得意なことや興味のあることを担当できるようにしています。」
高橋さん「ゲーム性などのアイデアを出すときには、それぞれがこれまでに遊んだゲームの中で『面白い』と感じた部分を思い出しながら、それを参考にしてみんなに共有するようにしています。学年に関係なく、誰でも自由に意見やアイデアを出せる、話しやすい雰囲気があるチームです。」

作品づくりがきっかけで生じた「防災意識」への確かな変化
―活動する中でワクワクしたこと、逆に難しいなと感じた点、苦労したことなどあれば教えてください
市川さん「最初に皆で集まって、実際にメタバースをプレイしたときのことです。はじめは操作方法が分からず、戸惑うこともありました。でも、プレイを続けていくうちに、『こんなこともできるんだ!』という新しい発見があって、その瞬間はとてもワクワクしました。」
富塚さん「難しいなと感じた点は、唯一無二のゲームを作ることです。多くの人に楽しんで防災を学んでもらおうとゲーム性を追求しているのですが、どうしても参考にしたゲームの影響を受けて、少し似たものになってしまうことがあります。他のゲームの良いところを取り入れつつ、オリジナリティのある作品にするのは、とても難しいと感じています。」
眞弓さん「苦労したのは、『どうすれば防災のことを分かりやすく伝えられるか』という点です。私自身、最初は防災の知識がほとんどなかったので、インターネットで調べたり、ハザードマップを見たりして、少しずつ理解を深めていきました。また、仮想空間を作っているメタバースについても同じで、最初は分からないことばかりでしたが、チームのメンバーや水澤先生と情報を共有しながら、少しずつスキルを身につけていきました。」
―ワクワクや苦労の積み重ねの中で、郡山防災マップは作成されているんですね。皆さんの防災意識に変化はありましたか
市川さん「活動を始める前は、防災の大切さは知っていたものの、『なんとかなるだろう』と少し楽観的に捉えている部分もありました。しかし、防災についてしっかり学び、知識を得ることで、これまで気づかなかったことがたくさんあると感じました。たとえば、避難場所について自分が理解していれば、家族や友達にも伝えられますし、一緒に出かけたときには『ここは危ない場所だよ』と教えることもできるようになりました。」
眞弓さん「この活動が、自分達の町について改めて考えるきっかけになりました。これまで、防災のことについてはどこか見て見ぬふりをしている部分が多かったと気づきました。実際に防災について向き合うことで、自分自身の意識が大きく変わり、防災の大切さを真剣に考えるようになったのがとても良かったと思います。」


郡山防災マップを“伝える”“届ける”。
メンバー皆が考える今後の展望とは
―後輩の皆さんにお聞きしたいのですが、先輩の作品を初めて見たとき、どのような印象を持ちましたか
高橋さん「自分がよく行っていた郡山駅がバーチャルの世界で、細かいところまで再現されていて驚きました。同時に、『自分達にもこんな素敵な作品が作れるのかな』と少し不安になりました。でも、メタバースの世界で防災マップを作ることで、子どもから大人まで親しみやすく、楽しく学べるものが作れることは素晴らしいことだと思います。これからの作品づくりでは、そうしたメタバースならではの良さを、もっと活かせるよう作品づくりに取り組んでいきたいです。」
―先輩から引き継いでいくこの作品を後輩の皆さんの手で今後どのように発展させていきたいとお考えでしょうか
富塚さん「cluster(クラスター)は、誰でも参加できるバーチャル空間のプラットフォームです。世界中の人とリアルタイムで交流したり、さまざまなコンテンツを楽しんだりできるのが特徴です。私達は、このclusterを使って、ゲーム性の追求など郡山防災マップの内容をさらに工夫していきたいです。また、足が不自由な方にも使ってもらえるような対応や、外国の方のために多言語対応にも挑戦していきたいと思っています。」
―では、今後の活動について具体的な展望を教えてもらえますか
市川さん「今後の活動としては、対象年齢として想定している小学校にまだ行けていないので、実際に出向き、郡山防災マップを体験してもらう出張授業をしたいなと思っています。また、郡山防災マップのVRを体験するだけでは小学生には少し難しいかもしれないと思いますので、体験前に防災クイズを出して、その両方で防災について学べるように工夫したいです。」
眞弓さん「現在は、郡山駅周辺の防災マップのみを制作していますが、今後は防災に取り組んでいる他の学校とも協力しながら、福島県内や全国のさまざまな地域に対応した防災マップを、メタバース空間で広げていけたらと考えています。また、9月に開催される<ふくしまSDGs未来博>にも出展を予定しており、防災マップや学校のメタバース空間の展示を行う予定です。」

活動を引き継ぐ後輩達に今、伝えたい想い。
―活動を通して得たことを、将来どのように活かしていきたいか、また後輩の皆さんにどんなことを伝えたいですか?
眞弓さん「防災についての知識をメタバース空間で表すことで、誰もが分かりやすく防災を学べることを私自身、実感しました。大学では地域に密着してさまざまなことを学びたいと思っていますし、将来は防災や教育といった分野で、地域の人が安心して暮らせる社会に貢献できる仕事に就きたいと考えています。
後輩達には、自分達の行動が周りや社会を変えるきっかけになることがあるということを学んで欲しいです。私も最初は、防災やメタバースの知識が無かったので不安はありましたが、水澤先生からアドバイスをもらったり、チームの皆と協力して完成に近づけていく上で自分自身成長したなと感じることが多かったです。だから1、2年生の皆さんには進めていく上で大変なことや不安なことなどたくさんあると思いますが、諦めたり投げ出したりせずにチャレンジし続けて欲しいなと思います。」
―最後に、水澤先生から見て皆さんが活動を通して成長したなと感じた点などお聞かせください
水澤先生「そうですね。まさに今このインタビューを通しても、生徒たちの成長を実感していますが、特にそれを強く感じるのは、市のイベントに出展したときなど、小学生への対応を見たときです。授業の中では、どうしても私達が教えて、生徒が受けるという受け身の学びが中心になりがちです。しかし、外部のイベントに出て、さまざまな人と接点を持ち、時には葛藤しながらも自分なりに対応している姿を見ると、生徒達が大きく成長しているのが分かります。
生徒達は本当に素直で、柔軟にいろいろなことを吸収していきます。大人の方が、先が見えないことに対して尻込みしてしまう場面もありますが、彼女達は迷いながらも前向きに取り組んでくれる。その姿勢がありがたいです。こういう取り組みに参加してもらえること自体が貴重ですし、大きな意味があると思っています。
アワードの授賞式を見させていただいたときも印象的でした。各校の生徒が、他の学校の発表を見ながら『こんなことを考えているんだ』と刺激を受けていて、気づきや意識の変化が起きていました。そうした経験が、『じゃあ自分達はどうする?』という問いに繋がっていき、次の行動へのきっかけになるのだと思います。
コロナ禍では、せっかく企画しても何も実現できなかった時期があったので、今はとにかく外に出て、人と関わりながら、多くのことを体験し、学び取ってほしいと思っています。最終的には、そうした経験が自分自身の進路や人生に活かされていけば、とても嬉しいです。
実は生徒達は、防災マップの活動だけでなく、郡山のブランド野菜を広めるプロジェクトや、廃棄食材を活用したレシピをJAと協力してお店で配布する取り組みなど、さまざまな企画に挑戦しています。忙しくて目が回りそうなこともあると思いますが、一つひとつの活動にしっかり向き合って取り組んでくれているので、その経験は確実に、皆の成長に繋がっていると感じています。」
取材を終えて
東日本大震災を幼稚園で経験した皆さんが、成長し、今では多くの人に防災を「自分ゴト」として捉え、いざという時に備えてほしいという強い想いを持って活動している姿が、とても印象的でした。メタバースやVRという技術を活用し、楽しみながら防災を学ぶという新たなアプローチは、これからの若い世代に多くの“気づき”をもたらしていくのだろうなと強く感じました。
これからも「防災ガールズ」の皆さんのご活躍を、心から楽しみにしております。






